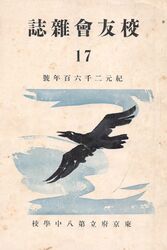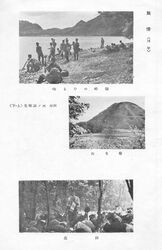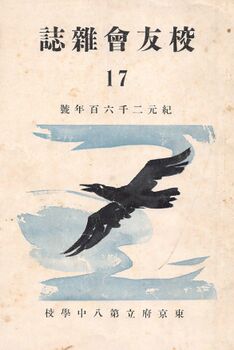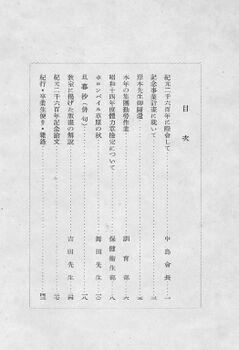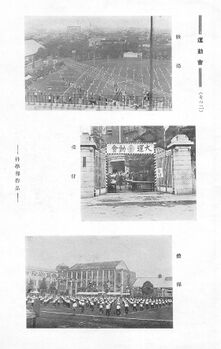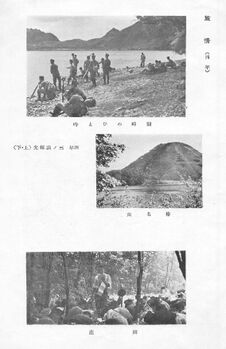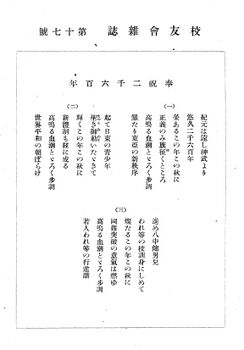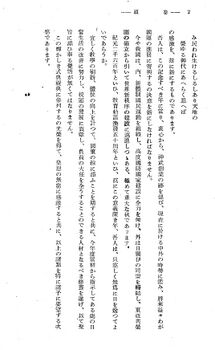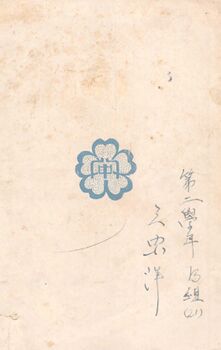「1940年度 (昭和15年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 54行目: | 54行目: | ||
:07.21 夏期鍛錬期間諸行事開始(集団勤労、学科講習、御宿臨海学校、運動競技剣道等) | :07.21 夏期鍛錬期間諸行事開始(集団勤労、学科講習、御宿臨海学校、運動競技剣道等) | ||
:08.28 転入学考査、合格者:一年 12名、二年 4名、三年 3名、四年 1名) | :08.28 転入学考査、合格者:一年 12名、二年 4名、三年 3名、四年 1名) | ||
:09.02 始業式、興亜奉公日行事実施 | :09.02 始業式、興亜奉公日行事実施 | ||
:09.05 正副級長任命式、防空演習実施 | :09.05 正副級長任命式、防空演習実施 | ||
| 82行目: | 81行目: | ||
:10.30 教育勅語渙発五十周年奉読式、学校長は教育功労者として文部大臣より表彰せらる | :10.30 教育勅語渙発五十周年奉読式、学校長は教育功労者として文部大臣より表彰せらる | ||
:10.31 午後講演(国民納税について。内務省理事官谷口壽太郎氏) | :10.31 午後講演(国民納税について。内務省理事官谷口壽太郎氏) | ||
:'''1941年''' | :'''1941年''' | ||
:03.08 卒業式 [[中14回 | 中14回生]](男子226名 | :03.08 卒業式 [[中14回 | 中14回生]](男子226名 | ||
==世相== | ==世相== | ||
:'''1940年''' | :'''1940年''' | ||
2025年3月10日 (月) 11:48時点における版
(編集中) (編集完了)
1940(昭和15)年度
できごと[1]
- 1940年
- 04.01 始業式、大島(英語)、加藤(國漢)、西尾(英語)、河原(教練)、河野(修身)諸先生新任式。興亜奉公日行事実施
- 04.02 入学式 中18回生(午後1時、帽章授与、及び入学生誓詞を本年より始む)
- 04.04 新旧生徒対面式。昼の全校体操(国民体操)本日より開始
- 05.05 正副級長、学級委員任命式
- 04.12 補習科合格者発表(117名/受験者123名中)
- 04.12 朝の講習開始(二、三、四、五年)
- 04.25 靖国神社臨時大祭(早朝参拝、行軍して明治神宮も参拝す)
- 04.29 天長節拝賀式挙行
- 05.01 興亜奉公日行事実施
- 05.01 結核予防、健康増進運動実施(~10)
- 05.04 全校マラソン挙行(多摩川堤防)
- 05.05 創立記念日
- 05.22 青少年学徒への勅語下賜記念日につき奉読式挙行
- 05.23 中間考査(~27)
- 05.27 海軍記念日、講演(今村海軍中将)
- 05.30 修学旅行出発(三年 箱根伊豆、四年 伊香保・太田、五年 甲府・富士五湖)(~06.01)
- 05.31 二年修学旅行出発(日光)(~06.01)
- 06.01 一年遠足(多摩御陵・高尾山)
- 06.01 更衣(夏服但し物資節約の為帽子に日覆を用いざる事とす)
- 06.07 一年 朝の講習開始
- 06.08 東亜競技大会出場(神宮外苑競技場にて五年60名 戦闘教練)
- 06.09 五年生習志野野営実施(~12)
- 06.16 保護者会及び保証人会。講演(補導協会主事藤岡氏)
- 06.18 模擬考査(四年、五年、補習科)及び実力考査(三年)
- 06.24 第13回卒業生記念樹(月桂樹)植付
- 06.26 満州国皇帝陛下御来訪につき学校長以下四年生16名奉迎
- 06.29 校内剣道大会
- 07.01 興亜奉公日行事実施
- 07.02 満州国皇帝陛下御退京につき奉送(高橋先生以下4年生16名)
- 07.07 支那事変三周年記念日(5年 武装行軍日比谷-靖国神社、4年以下は記念式及び閲兵分列式)
- 07.08 菅原先生御逝去(先生は東京高等師範剣道教授、本校剣道嘱託)
- 07.13 学期末考査(~18)
- 07.20 終業式
- 07.21 夏期鍛錬期間諸行事開始(集団勤労、学科講習、御宿臨海学校、運動競技剣道等)
- 08.28 転入学考査、合格者:一年 12名、二年 4名、三年 3名、四年 1名)
- 09.02 始業式、興亜奉公日行事実施
- 09.05 正副級長任命式、防空演習実施
- 09.09 節米のためパン食開始
- 09.13 水泳大会
- 09.14 短縮授業終了
- 09.15 満州国承認記念日
- 09.16 朝の講習開始(一年 64名、二年 61名、三年 45名、四年 23名)
- 09.17 模擬考査(四年、五年、補習科)
- 09.18 故北白河宮永久王[2]殿下御衷儀(午前10時30分遙拝黙祷)
- 09.20 校医(歯科)酒泉氏紹介式
- 09.23 秋季皇霊祭[3]
- 09.28 日独伊同盟成立につき訓辞。放課後学年別行軍
- 09.30 岸本先生御凱旋(満2年中支北支に転戦。午前6時品川駅に出迎え)
- 10.01 興亜奉公日行事実施、体力章授与
- 10.02 防空演習(~05)
- 10.05 学芸会(一、二、三年)、見学(四年 帝室博物館、科学博物館、五年 東日天日館、東日新聞社)
- 10.12 戊申詔書[4]、軍人援護勅語奉読式、及び訓話
- 10.13 大政翼賛、三国同盟国民大会に参加(三年150名 芝公園)
- 10.14 銃後奉公強調週間の行事として古鉄献納及び慰問文作製
- 10.16 四年、五年宮城内外苑勤労奉仕
- 10.17 新嘗祭、五年、一、二年宮城内外苑勤労奉仕
- 10.18 靖国神社臨時大祭につき休業。御親拝午前10時15分に遙拝黙祷
- 10.20 紀元二千六百年奉祝運動会
- 10.23 靖国神社、明治神宮参拝(全校生徒)
- 10.25 中間考査(~31)
- 10.30 教育勅語渙発五十周年奉読式、学校長は教育功労者として文部大臣より表彰せらる
- 10.31 午後講演(国民納税について。内務省理事官谷口壽太郎氏)
- 1941年
- 03.08 卒業式 中14回生(男子226名
世相
- 1940年
- 09.27 日独伊三国同盟成立
- 1941年
- 01. 食糧増産に青少年学徒を動員
- 流行語-ぜいたくば敵だ・一億一心
- 流行歌-湖畔の宿・隣組
戦時下の学校生活
自由の名残
私が八中に入学したのは、昭和十一年であるが、二年生の時に岡田校長から中島校長に替わった。
或る日、「上級生が新校長に抗議のストライキをするといって屋上に集まっている。下級生も集まれ。」とハッパをかけられた記憶がある。何のことかも分からぬうちに、事は立ち消えになったようであったが今から思えば、それは、当時まだ幾らか残っていた自由の校風のそよぎであったのだろう。
興亜奉公日
この年、昭和一二年には、日華事変が勃発し、その後、軍国主義の風潮は加速化していった。昭和一四年九月から、毎月一日を「興亜奉公日」と定めて、国民は「戦場の労苦を偲んで、奉公の誠をいたす」ことになった。
八中でも、その日は、朝礼が三〇分繰上げられて、宮城遙拝、黙祷、青少年学徒への勅語の奉読等があり、放課後には、全校生徒の閲兵、分列行進を行うのが慣例となった。
体力錬成
昭和十五年には、紀元二千六百年式典が挙行され、その前後に、勤労奉仕で、宮城前の清掃に出たことがある。また、神宮外苑運動場の競技大会で、戦闘訓練をやって、何だか場違いな感じがしたこともあった。
この頃に、各人に「体力手帳」が交付された。今も手もとに残っているが、昭和十五年から十八年の学徒動員で入営する前までの私の体位等が記録されている。懸垂や投てきが苦手で苦労した体力検定の想い出と共に、体力錬成が至上命令であった当時の記念品である。
(岩瀬達弥 中14回「創立60周年記念誌」P124)
教職員
| 職名 | 担任学科 | 氏 名 | 就 任 | 本籍地[5] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校長 | 岡田 藤十郎 | 1923/01/15 | 愛知県 | ||
| 配属将校[6] | 内田 辰雄 | 1927/03/16 | 熊本県 | ||
| 教諭 | 修身 | 修身 | 岩崎源兵衛 | 1923/03/15 | 東京府 |
| 修身、国漢 | 鈴木 鶴吉 | 1926/03/31 | 茨城県 | ||
| 修身、国漢、法経 | 岩本 實次郎 | 1923/04/12 | 愛知県 | ||
| 国漢 | 臼杵 東峻 | 1923/04/05 | 熊本県 | ||
| 手塚 昇 | 1924/03/31 | 栃木県 | |||
| 尾見 修一 | 1926/03/31 | 茨城県 | |||
| 宮下 幸平 | 1927/03/31 | 群馬県 | |||
| 田波 又男 | 1927/03/31 | 栃木県 | |||
| 岸本 美之留 | 1930/04/07 | 東京府 | |||
| 高野 正巳 | 1930/09/19 | 長野県 | |||
| 国漢(習字) | 斎藤 梅雄 | 1924/03/31 | 東京府 | ||
| 社会 | 地理 | 児玉 貞臣 | 1923/02/23 | 島根県 | |
| 歴史 | 山本 義夫 | 1924/03/31 | 長野県 | ||
| 甲藤 太郎 | 1926/03/31 | 高知県 | |||
| 歴史、地理 | 都築 秀徳 | 1925/03/31 | 高知県 | ||
| 数学 | 栗原 善範 | 1923/04/30 | 神奈川県 | ||
| 飯野 兼八 | 1924/03/31 | 東京府 | |||
| 高輪 休郎 | 1925/05/15 | 東京府 | |||
| 崎谷 巖 | 1926/03/31 | 栃木県 | |||
| 沼尻 源一郎 | 1927/03/31 | 茨城県 | |||
| 理科 | 博物[7] | 北見 宗吉 | 1923/04/05 | 東京府 | |
| 一瀬 義行 | 1925/03/31 | 東京府 | |||
| 物化 | 桑野 達平 | 1925/03/31 | 福岡県 | ||
| 峯岸 政之助 | 1930/03/31 | 埼玉県 | |||
| 英語 | 伊藤 義末 | 1923/03/30 | 千葉県 | ||
| 大伴 峻 | 1924/03/31 | 東京府 | |||
| 斎藤 幸之助 | 1926/03/31 | 埼玉県 | |||
| 川波 千尋 | 1926/03/31 | 福岡県 | |||
| 百田 治朗 | 1926/03/31 | 山梨 県 | |||
| 大竹 健夫 | 1927/03/31 | 東京府 | |||
| 体操 | 加藤 譲 | 1923/04/10 | 岐阜県 | ||
| 岐部 信之助 | 1924/02/11 | 静岡県 | |||
| 市野 保 | 1924/03/31 | 東京府 | |||
| 峰岸 徳哉 | 1927/03/31 | 群馬県 | |||
| 芸術 | 図画 | 麻生 秀二 | 1923/03/31 | 東京府 | |
| 唱歌 | 松井 力 | 1925/03/31 | 東京府 | ||
嘱託・学校医
| 教科 | 氏名 | 就任 | 本籍地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 嘱託 | 国漢 | 龜山 與市 | 1925/06/20 | 岐阜県 | |
| 斎藤 芳滋 | 1927/03/31 | 東京府 | |||
| 福村 清 | 1929/03/31 | 大分県 | |||
| 数学 | 奈良 善雄 | 1926/03/31 | 青森県 | ||
| 赤沼 實 | 1929/10/09 | 長野県 | |||
| 理科 | 博物 | 岸谷 貞治郎 | 1925/03/31 | 大阪府 | |
| 英語 | 佐藤 浩 | 1924/03/31 | 山形県 | ||
| ヘンリー・マーフォート・ケーリー | 1926/04/01 | 米国 | |||
| 長見 久堅 | 1929/03/31 | 島根県 | |||
| 山口 孝 | 1929/04/09 | 千葉県 | |||
| 体操 | 森田 文十郎 | 1925/03/31 | 埼玉県 | ||
| 佐藤 留五郎 | 1927/03/31 | 福島県 | |||
| 芸術 | 図画 | 吉田 雄司 | 1927/05/09 | 千葉県 | |
| 学校医 | 岡田 省三 | 1926/09/18 | 東京府 | ||
書記
| 職 名 | 氏 名 | 就 任 | 本籍地 |
|---|---|---|---|
| 書記 | 佐藤 正男 | 1924/02/20 | 東京府 |
| 永山 政信 | 1924/04/05 | 茨城県 | |
| 平野 義包 | 1927/03/15 | 愛知県 |
学芸会
- 10月5日(土)午前8時より(1、2、3年のみ)
- 開会挨拶
- 閉会挨拶
運動会
- 10月20日(日)紀元二千六百年奉祝運動会
- 運動会詳細については「校友会雑誌 第17号」P89から記載されています。
「校友会雑誌 第17号」紀元二千六百年号
- 「校友会雑誌 第17号」は、1940(昭和15)年12月22日発行されました。
- 中17回 三宮 洋 様より寄贈いただきました。
 「校友会雑誌 第17号」紀元二千六百年号 全文
「校友会雑誌 第17号」紀元二千六百年号 全文
- 以下のリンクから「校友会雑誌 第17号」全文をご覧いただけます。
- 「校友会雑誌 第17号」PDFファイルへのリンク
卒業アルバム
関連項目
*← 1939年度 (昭和14年度) *→ 1941年度 (昭和16年度)
脚注
- ↑ 1940(昭和15)年4月~10月については、「校友会雑誌 第17号」P68からの学校歴から転記しました。
- ↑ 北白河宮永久王(きたしらかわのみや ながひさおう、1910(明治43)年2月19日 - 1940(昭和15)年9月4日)は、日本の皇族。陸軍軍人、貴族院議員。北白川宮成久王の第1王男子。最終階級は陸軍砲兵少佐(薨後特進)。母は明治天皇の第7皇女房子内親王。妃は男爵徳川義恕の次女祥子。参謀たる陸軍砲兵大尉として蒙疆方面(モンゴル及び中国北部)へ出征していたが、演習中に航空事故に巻き込まれ殉職した。
- ↑ 毎年秋分の日に、皇霊殿で、歴代の天皇、皇后、皇親などの霊をまつる祭儀。もと国家の祭日であった。現在の国民の祝日「秋分の日」にあたる。
- ↑ 戊申詔書(ぼしんしょうしょ)は、1908(明治41)年戊申の年に出された明治天皇の詔書。日露戦争後の個人主義・社会主義の盛行を戒め、国民に勤倹を求めた。この詔書をきっかけに地方改良運動が本格的に進められ、学校教育でも教育勅語と並ぶものとされ、国民に大きな影響を与えた。
- ↑ なぜか「本籍地」が記載されています。
- ↑ 旧日本陸軍で、学校教練のため陸軍現役将校配属令などにより官公私立の中学校、高等学校、大学予などに配属された将校。
- ↑ 明治、大正、昭和初期までの小学校、中学校の動植物・鉱物を内容とする教科の名称。
・
2025年3月10日:直近編集者:Hosamu
TimeStamp:20250310114842